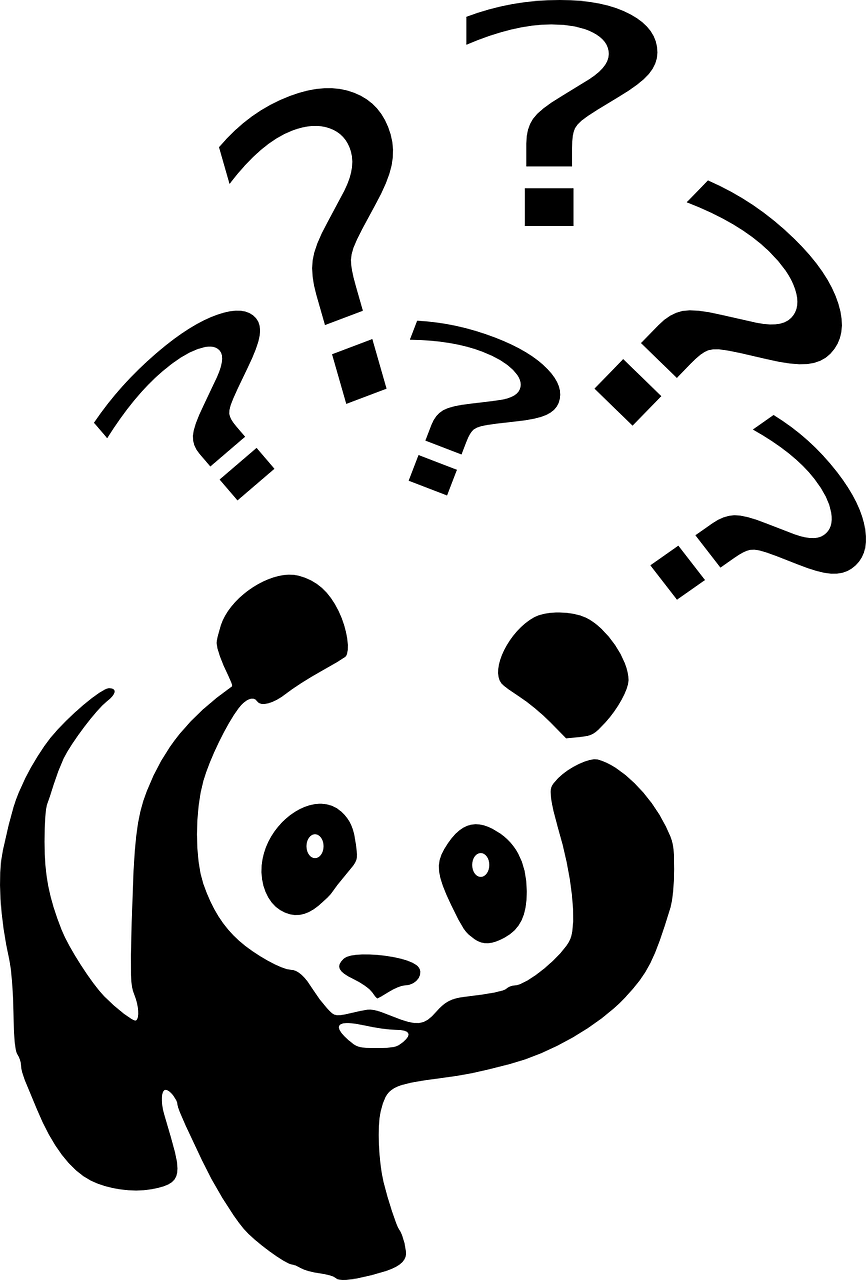CHOWA(ちょうわ)ウエディング代表の藤田将悟です。
今回は、結婚式場の「持込料」と、結婚式場の利益の仕組みをお話したいと思います。
初めにこの情報を知っていると知らないでは、結婚式費用と質に大きな差が生まれますので、最後までじっくり読んで知識を深めてください。
プランナーのもうひとつのお仕事とは?
結婚が決まるといろいろな式場の情報集めをしたり、式場のフェアに参加して見積もりをもらうと思いますが、
「見積もりの金額より実際に支払う費用が高かった!」
というのは、今までの先輩カップルの話でもよく話題に上がります。
なぜそのようなことになるのでしょうか?
結婚式場を探しているカップルの多くは、数か所の式場を比較検討することが多いと思いますが、その比較の中でも「価格」の面が、式場を決定する際の大事な検討材料になります。
結婚式場もそのへんは心得ているので、見積もりを出すときは
「最低価格」
で見積もりを出します。
次に、その見積もり価格で比較検討してもらい、自分の式場を選んでいただくことが担当プランナーさんのお仕事になります。
プランナーさんは新規のお客様を獲得することと、獲得したお客様にオプションを増やしてもらい
「お支払い金額を上げる」
ことでお給料が変わります。
※すべての式場ではありません。
担当プランナーさんは「お見積書に記載されている○○は最低限の物ですので、ゲストの事を考えてワンランク上のものにしてみてはいかがでしょうか?」と提案します。
結婚式場は慈善事業ではなく、あくまでもビジネスです。
プランナーさんには会社に利益を残すことも要求されています。
そのオプションが本当に必要な事なのかじっくり見極めなくてはなりません。
結婚式場は儲かっている?
見積もりの中のドレスや写真、そしてもちろん引き出物までが、外部からの持ち込みを禁止しています。
また、禁止ではなかったとしても「持込料」との名目で請求されることは皆さんご存知の事と思います。
これは、提携の業者から支払われる紹介料がなくなる代わりに、お客様であるはずの新郎新婦に
「利益の肩代わり」
をさせるということです。
理不尽なシステムなのにまかり通っていることが実に残念でなりません。
CHOWAウエディングの中心サービスである引き出物の宅配 「手ぶらギフト」は、引き出物をはじめから式場へ持ち込まないので、持込料はかかりません。
しかし中には、「引き出物を持ち込まなくても持込料がかかります」と、堂々と請求する式場もあるようです。
もう意味が分かりませんよね。
また、ドレスやお花、写真、引き出物など全てを式場提携の業者を利用する事を前提で「○○万円引き」とされているところもあるようです。
ビジネスとしてとてもうまいやり方だと思いますが、式場の一方的な決まりに縛られた挙式しかできないという事が、本当の意味での
「新郎新婦の理想の結婚式」
とかけ離れたものに思えてなりません。
交渉することで免除もある?
そのような場合でも、プランナーさんと交渉することで免除していただけることもあるようですので、まずはじっくりと相談してみてください。
「親戚が引き出物ショップ経営しているからどうしても・・・」とか(笑)
それでも応じてもらえない場合や、そもそも契約の時点で持ち込み料などの話を聞いていなかった場合は、
「独占禁止法」や「消費者契約法」
に違反している可能性が高いので、法律を持ち出して話を進めてみるのもひとつの方法です。
プランナーさんとの関係悪化は避けたいと思われるでしょうが、不満があるままの挙式はもっと避けるべきです。
外部業者から買うメリットは?
結婚式場の提携業者から引き出物を購入すると、業者から式場への紹介料が発生します。
「CHOWAウエディング」のような外部の引き出物販売業者は式場と業務提携していませんので紹介料は発生しません。
その為、お客様への充実したサービスの提供が可能となるわけです。
本当は引き出物は安くお得に買えるのです。
ただ皆さんその事実を知らないだけなんです。
最後に
結婚というおめでたい行事の前にお金の話になってしまいましたが、これからのお二人の生活資金の事も考えると、節約できるお金は少しでも節約して頂こうと思い、今回の情報をお伝えしました。